言葉を持たない犬は行動や仕草などで感情を伝えてくれます。そして、犬同士にもコミュニケーションをとる方法があります。犬同士が仲良くなる方法についてまとめました。
犬同士のコミュニケーション
ほとんどの犬が相手の仕草から感情を読み取って会話をしています。
犬の中には人間は好きだけど他の犬が苦手という犬もいます。これは子犬の頃の経験不足で、十分な社会性が身についていなかったことが原因として多いといわれています。犬同士にも相手との相性があります。
飼い主同士が犬同士を仲良くさせたいと思っても、相性が合わず仲良くできない場合があることは理解しておく必要があります。犬にとって相手が仲良くできる相手であるのか飼い主として見極めが必要です。
それを判断するために、まずは犬同士がどのようなコミュニケーションをとっているか、犬のしぐさを覚えておきましょう。
1. しっぽの動き
しっぽの動きから犬が今どう思っているか判断することができます。
「喜び・嬉しさ・親愛」の気持ちの時はしっぽを振ります。しかし、普段よりも高くしっぽを上げている時は「警戒・威嚇」の意味が含まれている場合があります。
しっぽを振っているから喜んでいる、攻撃的な意思はないと判断すると、犬同士の喧嘩が始まることがあるので要注意です。
2. 声のトーン
犬が吠えることは攻撃や威嚇の感情と捉えがちですが、全てがそうだとは限りません。
高いトーンで弾むような鳴き声や、目が輝き口元が緩んでいる場合は「嬉しさや喜び」の時です。
低いトーンの声の場合は「緊張や警戒・警告」などを表現しています。その場合は体全体に緊張があり耳もピンと立っていることが多いです。
3. ニオイの嗅ぎ合い
犬同士の代表的なコミュニケーション方法の1つに「おしりのニオイを嗅ぐ」行為があります。
犬の肛門には肛門腺という器官があり、そこから出る分泌液に様々な情報が含まれているといわれています。「性別・年齢・強さ」などが瞬時に分かるそうです。
そのため、おしりのニオイを嗅ぐ行為は犬同士の挨拶なのです。子犬の頃から嗅がれることを嫌がらないようにしておくと良いでしょう。
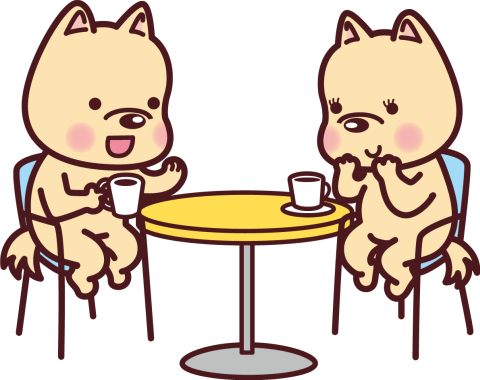
犬同士を仲良くさせる方法
相性の悪い犬同士を無理に仲良くさせようとすることは避けるべきですが、初対面の犬同士が仲良くなれるように飼い主がフォローすることは可能です。犬同士を仲良くさせるポイントを紹介します。
1. まずは距離を保つ
まずはお互いの距離を保ちましょう。
犬同士が直接接触できない程度の距離を保ちお互いを観察させます。リードは飼い主のそばをウロウロできるぐらいの長さが良いです。
2. 犬の仕草を観察
次に犬の仕草を観察しましょう。次のような相手の犬を無視した行動がみられた場合は、攻撃などの敵意がないことを相手にアピールしている状態だといえます。
このような行動も実は犬同士の会話なのです。お互いに争う姿勢がないことを確かめることができれば、不安が減り安心した心の状態になっていきます。
3. 接触させてみる
お互いに落ち着いた状態になってきたらゆっくり近づきます。犬同士がお尻のニオイを嗅ぎあったら静かに見守ります。
4. 仲良くなっても油断しない
お互いにニオイを嗅ぎあったら仲良くなれたということなのですが、油断せずに注意して見守りましょう。
ニオイを嗅がなかったりジャレ合わない場合、または相手の犬が怖がる場合は仲良くなれなかったと判断してその場から去りましょう。しばらくニオイを嗅ぎ続けるときは仲良くなれたと思って良いでしょう。
まとめ
愛犬が他の犬と仲良くなることは飼い主さんにとって嬉しいことだと思います。
犬にも個性があるので一概には言えませんが、犬のコミュニケーション方法を知ることは犬同士の相性や犬の気持ちを理解することに繋がります。犬同士が喧嘩にならないよう、無理にお互いを近づけることは避け、しっかり手順を踏み、様子を見ながら判断をしましょう。
愛犬のことを普段からよく観察し、性格を把握し、判断できることが飼い主として大事なことです。


